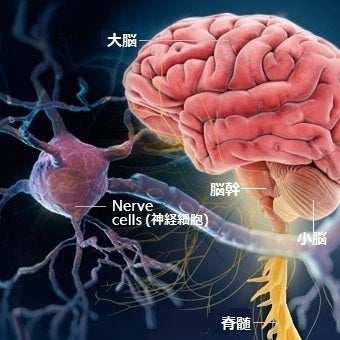ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社(BMS, 本社:東京都新宿区)は12月19日、3種類の直接作用型抗ウイルス剤(DAA)を配合した経口治療薬「ジメンシー®配合錠」(Ximency=一般名:ダクラタスビル塩酸塩/アスナプレビル/ベクラブビル塩酸塩)について、セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎、又はC型代償性肝硬変に於けるウイルス血症の改善の適応で、厚生労働省より製造販売承認を取得したと発表した。
C型肝炎は、現在日本では、190万~230万人がC型肝炎ウイルス(HCV)に感染しているとされています。
日本赤十字血液センターで、初めて献血を行った方(初回供血者)3,748,422人のHCV抗体陽性率は、全体で0.26%でした。
高齢になるほど頻度は高く、2005年時点の60~69歳では1.18%に昇っています。(日本赤十字社資料より)
感染経路は母子感染によるものと、血液を介しての感染に別けられますが、C型肝炎の場合はB型肝炎ウイルスと異なり、母子感染は多くはありません。
現在、C型肝炎ウイルスに感染している方の殆どは、過去の輸血や注射が原因です。
以前のように、医療現場での注射針の使い回しも行われる事は無く、最近ではピアスの穴開けや、医療現場での不注意な針刺し事故などによる感染が見られます。
C型肝炎ウイルスは、B型肝炎ウイルスより感染力は弱く、性交渉や体液で感染する事は殆どありません。
【注意、性交渉で感染すると言う記述のWebサイトがありますが、それはB型肝炎の場合であり、C型肝炎では多くはありません】
(国立感染症研究所 IDWR 2011年 第21号「速報」、及びブリストル・マイヤーズ スクイブ(株)HPから抜粋)
C型肝炎ウイルス(HCV)に感染すると、約3割は自然にウイルスが排除されますが(一過性感染)、約7割は持続感染に移行します。
持続感染は、感染したウイルスが、身体から排除されず、肝臓の中に住みつく事で、一部の人は慢性肝炎を発症します。
「ジメンシー®配合錠」は、米国ブリストル・マイヤーズ スクイブ社が開発したNS5A複製複合体阻害剤である「ダクラタスビル塩酸塩」、及びNS3/4Aプロテアーゼ阻害剤である「アスナプレビル」に、新規DAAである「ベクラブビル塩酸塩」を配合した固定用量配合の抗ウイルス薬です。
新規DAAである「ベクラブビル」は、非構造蛋白5B(NS5B)ポリメラーゼに対する非核酸系阻害剤であり、作用点の異なる“ダクラタスビル”及び“アスナプレビル”に「ベクラブビル」を追加することで、相加・相乗効果、及び耐性発現の抑制効果が認められています。
作用点の異なる3種類のDAAを配合した製剤としては、日本初となります。
国内第Ⅲ相試験において‥‥
ジェノタイプ1bのC型慢性肝炎、又はC型代償性肝硬変患者に於ける「ジメンシー投与群」のSVR12(投与終了から12週後のHCV RNAが定量下限未満)達成割合は95.9%(95%信頼区間:90.8~98.7%)でした。
また、ジェノタイプ1a/1bのC型慢性肝炎及び代償性肝硬変患者の合計に於いても95.9%を示し、サブグループ解析では、年齢、性別、線維化の程度、前治療歴、代償性肝硬変の有無、IL28B遺伝子型などの背景因子、NS5A-L31、及びY93の耐性変異の有無に関わらず、優れた有効性が確認された。
【ジメンシーの製品概要】
【製品名】: ジメンシー®配合錠
【一般名】: ダクラタスビル塩酸塩/アスナプレビル/ベクラブビル塩酸塩
【効能又は効果】: セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
【用法及び用量】: 通常、成人には1回2錠を1日2回食後に経口投与し、投与期間は12週間とする。
【成分・含量】: 1錠中にダクラタスビル塩酸塩16.5mg(ダクラタスビルとして15mg)/アスナプレビル100mg/ベクラブビル塩酸塩39.6mg(ベクラブビルとして37.5mg)を含有する。
【主な副作用】: ジメンシーによる主な副作用は、ALT(GPT)増加が23.0%、AST(GOT)増加が19.4%、好酸球増加症が17.1%、発熱が16.6%、高ビリルビン血症が14.7%等でした。